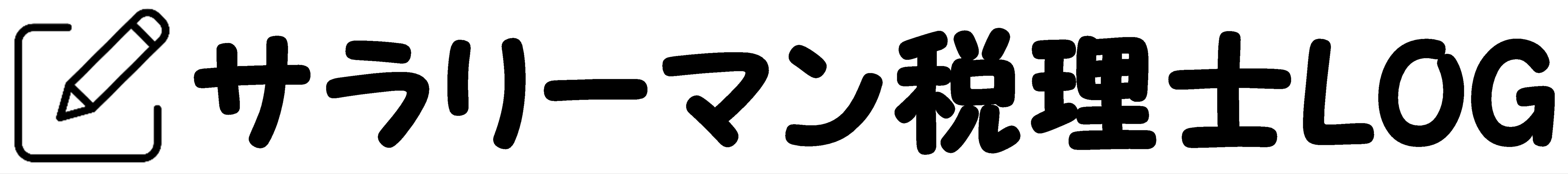こんにちは!
サラリーマン税理士のりゅうです。
今回は、法人加入の医療保険で保険金が下りた場合に、被保険者にお見舞金等を支給するときの取扱いです。
下りた保険金全額をお見舞金として支給してよいかというと、そうではありません。
法人加入の医療保険の論点はいくつかあって、
・法人支払の医療保険料の取扱い
・法人が保険金を受け取った場合の取扱い
・被保険者に見舞金等を支給する場合の取扱い
となります。
これらを簡単に解説します。
法人支払の医療保険料の取扱い
医療保険(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等)は第三分野保険と呼ばれ、基本的には全額損金となります。
ただし、2018年に法改正があり、法人税基本通達9-3-5も改正されました。
改正により、事業年度の支払金額が30万円以下であれば全額損金算入が認められ、30万円を超える場合には、一定の計算方法により一部損金となります。
ちなみに、30万円判定は、既存契約の保険を合算して判定するため、例えば25万円の保険と10万円の保険に加入している場合、合計35万円となるため、一定の計算方法により損金を計算することになります。(25万円の保険だけ全額損金とする、という取扱いはできません。)
(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
法人税基本通達9-3-5
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、特約が付されているものを含む。以下9-3-7の2までにおいて同じ。)又は第三分野保険(保険業法第3条第4項第2号《免許》に掲げる保険(これに類するものを含む。)をいい、特約が付されているものを含む。以下9-3-7の2までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(特約に係る保険料の額を除く。以下9-3-5の2までにおいて同じ。)については、9-3-5の2《定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い》の適用を受けるものを除き、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」、令元年課法2-13により改正)
(1) 保険金又は給付金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(注)
1 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
2 (1)及び(2)前段の取扱いについては、法人が、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る。以下9-3-5において「解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険」という。)に加入した場合において、当該事業年度に支払った保険料の額(一の被保険者につき2以上の解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に加入している場合にはそれぞれについて支払った保険料の額の合計額)が30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、これを認める。
法人が保険金を受け取った場合の取扱い
医療保険に加入している場合に、医療事故が生じたことによって、法人に保険金が支払われることがあります。
この場合の保険金は、保険料負担者(受取人)である法人が受け取り、法人の益金となります。
一般的には、雑収入(消費税→不課税)として処理します。
被保険者に見舞金等を支給する場合の取扱い
役員又は従業員を被保険者とする医療保険に加入している法人について、保険金の受取人を法人としている場合には、その保険金は法人の益金となります。
保険料支払者→法人(損金)
被保険者→役員又は従業員
受取人→法人(益金)
この場合、見舞金として被保険者へ支給する場合がありますが、その支給する見舞金が損金になるかどうかが論点となります。
見舞金等の支給は、通常社内規程によって支給されるケースが多いですが、社内規程の定めによる金額が全て福利厚生費として損金算入できるわけではありません。
つまり、見舞金の損金算入は、社内規程にどのように定められているかではなく、見舞金の額が「社会通念上相当であるか否か」により判断することが妥当という考えになります。
その考えの根拠は、【平成14年6月13日採決、裁決事例集No.63 309頁】において、国税不服審判所が、
「一般に、慶弔、禍福に際し支払われる金品に要する費用の額は、地域性及びその法人の営む業種、規模により影響されると判断されることから、当審判所においては、改定類似法人のうち見舞金等の福利厚生費の規定が存する8社についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、別表9のとおり、株式会社aにおいてはその規定で見舞金の上限を50,000円としており、株式会社cにおいては役員に対して50,000円の支払例があり、株式会社fにおいてはその規定において代表取締役社長を除く役員に対する見舞金の上限を50,000円としており、株式会社gにおいては代表取締役社長に見舞金として入院給付金の全額を支払った際その全額を同人に対する給与として処理しており、また、他の改定類似法人においてはその規定している額及び支払例において見舞金の額が50,000円を超えていないことから、法人の役員に対して支払われる福利厚生費としての見舞金の額は、入院一回当たり50,000円が社会通念上相当である金額の上限と認められる。」
「請求人は、Hに支払った見舞金は、会社規定により当然個人が受け取るべきものを支出しただけであり、いわば会社を経由した保険金の支払というべきものである旨主張する。
しかしながら、請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題であると解すべきである。
また、法人税法上、福利厚生費としての見舞金が損金の額に算入されるか否かは、当該見舞金の額が社会通念上相当であるか否かにより判断されるものであり、会社規定に従って支払われたものかどうか及び保険金の原資のいかん並びに会社規定の作成過程及び保険契約の締結過程のいかんによって左右されるものではない。」
と判断しているところによります。
ここでのポイントは、
・法人の役員に対して支払われる福利厚生費としての見舞金の額は、入院一回当たり50,000円が社会通念上相当である金額の上限と認められる
・請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題である
・法人税法上、福利厚生費としての見舞金が損金の額に算入されるか否かは、当該見舞金の額が社会通念上相当であるか否かにより判断される
・会社規定に従って支払われたものかどうか及び保険金の原資のいかん並びに会社規定の作成過程及び保険契約の締結過程のいかんによって左右されるものではない
となりますので、例え社内規程で「支給額の50%を見舞金として支給する」という文言があったとしても、税務上の取扱いはあくまでも「社会通念上相当であるか否か」により判断することになります。
見舞金の取扱い
50,000円が「社会通念上相当である金額の上限」とする場合に、80,000円を支払ったときは下記のような取扱いになると考えられます。
支払者側(法人)
・50,000円→福利厚生費
・30,000円→役員給与(損金不算入)又は給与(損金)
受取側(役員又は従業員)
・50,000円→給与課税なし
・30,000円→給与課税あり